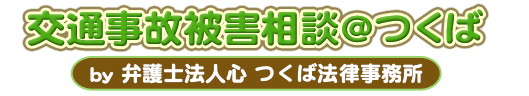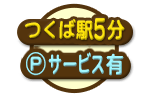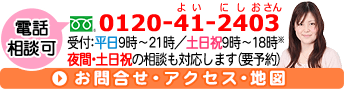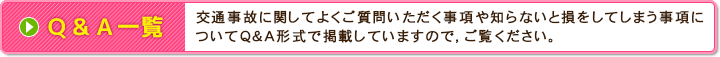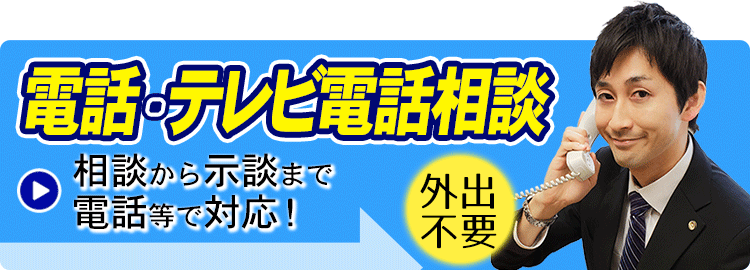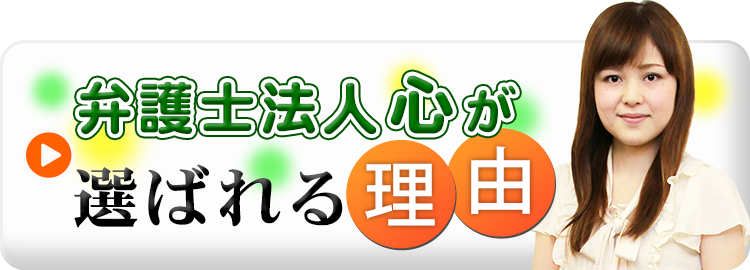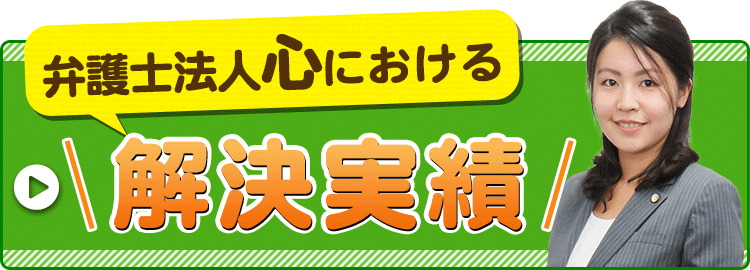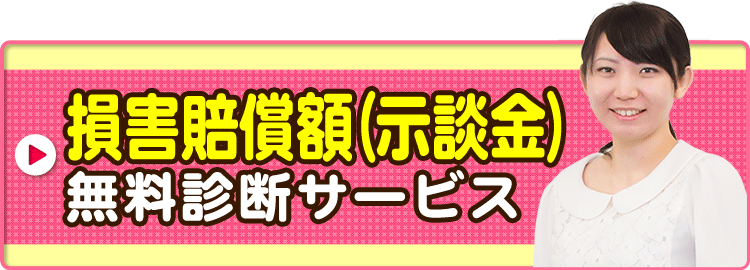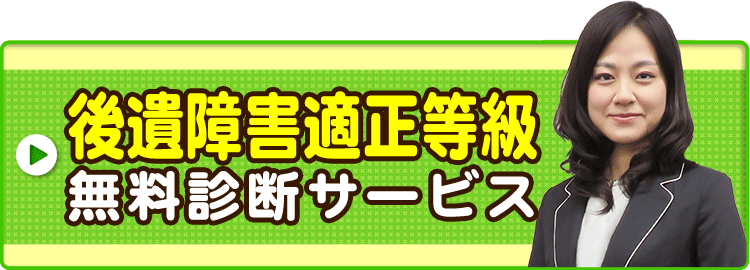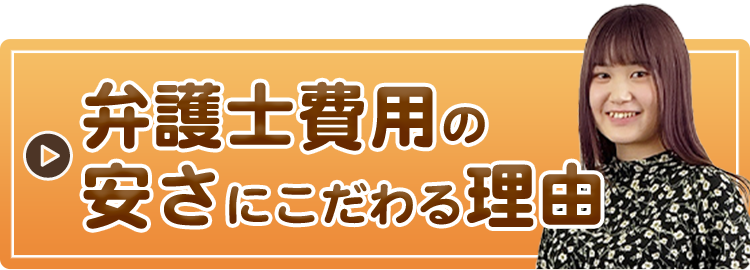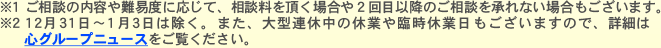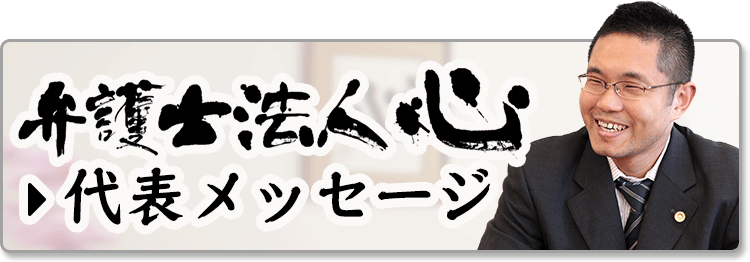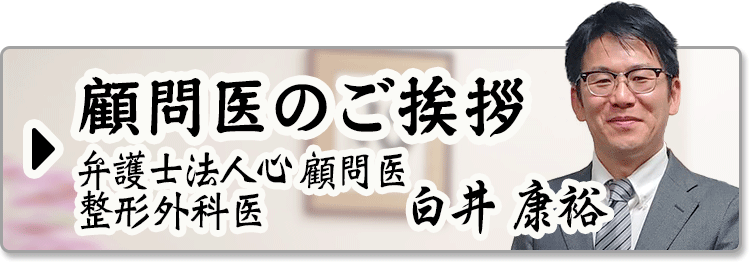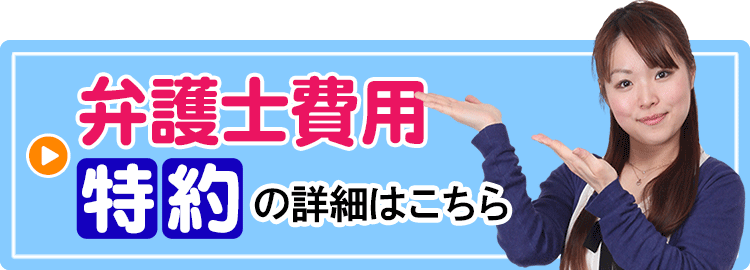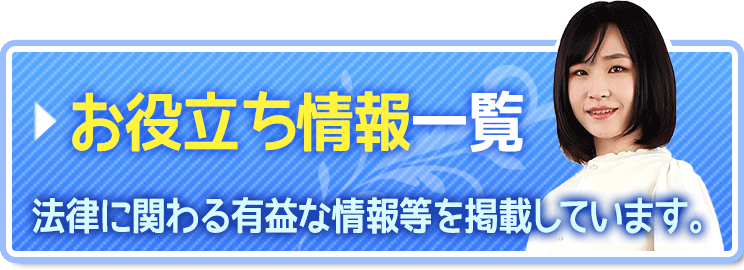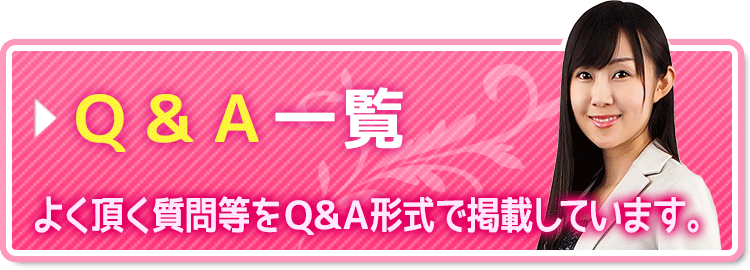もらい事故の慰謝料・示談金の相場
もらい事故の被害者になってしまった場合、ご自身が加入する保険会社は交渉を代理してくれることはありません。
そのため、被害者自身が加害者側の任意保険の担当者と示談交渉を行うことになります。
この場合、交渉格差が生じるため、事前に対策を考えておかないと、適切な金額の慰謝料(示談金)を受け取れない可能性があります。
今回は、もらい事故の慰謝料・示談金について解説します。
1 もらい事故とは?
⑴ もらい事故では過失割合が10:0
交通事故の多くは、当事者の両方に過失があるといわれています。
特に自動車同士の事故の場合などは、明らかに一方が交通違反をしていたとしても、もう一方にも前方不注意などの軽い違反がある事が多いのです。
この場合、全体の損害をどのように負担するのかが問題となります。
交通事故事案では、これを「過失割合」という概念を用いて解決していきます。
過失割合とは、当該交通事故における当事者の落ち度の度合いを示すものです。
実際上は、たとえば、加害者:被害者の過失割合7:3というように数字で表すことにより、責任の負担度合いを決めていきます。
被害者に100万円の損害がある場合で過失割合が上記のとおりだとすると、加害者は70万円の負担を負い、被害者は30万円の負担を負うことになります。
この場合は、加害者が被害者に対し損害である70万円を支払うことになるのです。
通常は、上記で表したように両者に責任がありますが、まれに加害者に100%非があるケースも存在します。
例えば、停車中に後ろから衝突されたようなケースです。
これを「もらい事故」と呼び、被害者が責任を負担することは一切ありません。
⑵ もらい事故被害者が知っておくべきポイント
もらい事故の場合は、いくつか注意しておくべきポイントがあります。
具体的には、以下の2点です。
- ・被害者の加入する保険会社の示談交渉代行サービスは適用されない
- ・もらい事故に限らず、物損事故の場合は慰謝料を請求できない
まず、冒頭でも述べましたが、もらい事故の被害者はご自身が加入する保険会社の示談交渉代行サービスを受けることはできません。
つまり、原則として被害者ご自身で相手方の保険会社と交渉を行うことになります。
被害者に過失がない場合、被害者が加入する保険会社は支払いをする必要がないため、示談交渉サービスを行う事が禁止されているのです。
というのも、他人の示談交渉を仕事として代理することができるのは弁護士だけであり、これを勝手に保険会社がやってしまうと非弁行為として違法となるからです。
次に、物損事故の場合は慰謝料を請求できない点です(これはもらい事故に限った話ではありません)。
物損事故でも慰謝料(精神的損害分の補償)を請求できると考えている方が多いですが、これは極めて例外的なケースです。
通常は慰謝料を請求することはできません。
2 もらい事故の慰謝料額について
⑴ 慰謝料と示談金の違い
まず、皆さんは示談金と慰謝料の違いをご存知でしょうか。
示談金とは、当事者同士が話し合いによって解決するために被害者に渡す損害賠償金全般のことを指します。
示談は和解の性質を持ち、当事者が自主的に紛争を解決する方法のことをいいます。
他方慰謝料は、その損害賠償金の項目の1つといえます。
損害賠償の中身としては、治療費、入通院慰謝料、休業損害、修理費用、入院雑費、後遺障害慰謝料、逸失利益など様々な項目があります。
この1つとして慰謝料(入通院慰謝料、後遺傷害慰謝料)があるのです。
つまり、慰謝料は損害賠償金(示談金)の中身の1つと言うことができます。
ちなみに、上記で示した損害賠償の中身は人身事故を想定したものです。
物損事故の場合は、原則として車の修繕費用、代車使用料、休車損害(営業利益に損害が出た場合のみ)等のみ請求できることとなります。
⑵ もらい事故の慰謝料相場(基準)
もらい事故が人身事故の場合、怪我を負った被害者の方は慰謝料を請求することが可能です。
事故の内容にもよるため、一概にいくらが相場ということはできませんが、慰謝料算出のための基準は存在します。
慰謝料の計算方法については、次の3つの基準が利用されています。
1つ目は、自賠責基準です。
もっともベーシックな保障であり、入院や通院日数1日につき4,300円が保障されます。
自賠責保険は、強制加入の保険であるため、任意保険に加入していない加害者からも受け取る事ができます。
もっとも、自賠責保険の傷害による損害に対する補償は120万円が限度となるため、保障が低廉になってしまうという問題があります。
次に、任意保険会社基準です。
加害者が加入する任意保険会社が独自の基準を設け、それに基づき慰謝料を算出してくれます。
自賠責保険と同程度かそれより少し高い態度の金額の保障を受ける事ができますが、被害者が受け取るべき適正額とは言い切れません。
というのも、任意保険会社は営利企業であるため、できるだけ示談金を安くまとめたいと考えているためです。
最後に、裁判基準です。
弁護士基準とも呼ばれています。
実際の裁判でも利用されている慰謝料算出基準であり、3つの基準の中で算出される慰謝料額が通常最も高額になる基準です。
被害者が受け取るべき適正額を算出する事ができますが、裁判をしたり弁護士に依頼したりしないとこの基準を利用できないという特徴もあります。
3 もらい事故で適正な損害賠償を受けるために
では、もらい事故で適正な示談金を受け取るためには、どのように対応するのが良いのでしょうか。
大前提として、たとえば事故直後に、問題のある部位全てについて、正しく初診・検査等を受け、その後も適切な頻度で通院すること等、各損害項目について適切な対処をしていくことが大事なことは言うまでもありません。
その上で、適正額の示談金(賠償金)を受け取るための正しい対応方法をお伝えします。
⑴ 交渉格差を埋めるため弁護士に依頼する
先にご説明したように、もらい事故の場合には、任意保険会社の示談交渉代理サービスを利用することができません。
そのため、被害者ご自身で任意保険会社の担当者と示談交渉を行うことになります。
しかし、相手は交通事故案件を毎日取り扱うプロであり、被害者が足元を見られてしまうことも少なくありません。
示談金が少なくなってしまう可能性を下げるためには、被害者も弁護士に交渉を任せるのがよいでしょう。
交通事故案件に精通した弁護士なら、交渉で任意保険の担当者と対等に話ができるだけでなく、有利に話を進めていくことも可能です。
また、弁護士に依頼すれば、事故後の早期のうちなら、先の述べた各損害項目についてもアドバイスをもらいつつ、対応していくこともできますし、治療が終わった後の交渉段階においては先程ご説明した弁護士基準での慰謝料計算が可能です。
基準が大きく上がるため、ご自身で交渉するよりも高額な慰謝料が請求できるでしょう。
特に、任意保険会社の提示した示談金額が少ないと感じたら、弁護士に依頼することをおすすめします。
⑵ 弁護士費用特約を活用する
「慰謝料は増額してほしいけれど、弁護士費用が心配…」という声もあるでしょう。
確かに、弁護士に依頼すると弁護士費用がかかってしまうため、費用倒れを起こさないように考えなければいけません。
できるだけコストを抑えるためには、ぜひ弁護士費用特約を活用してください。
弁護士費用特約とは、自動車保険に付帯するオプションの1つであり、交通事故に関わるトラブルにつきかかる弁護士費用を保障してくれるものです。
1つの事件に対し、多くの場合約300万円まで費用を負担してくれるため(保険会社との契約内容により異なります)、被害者は弁護士費用を負担する必要がなくなります。
「加入していない」と思われる方が多いのですが、実際は自動車保険加入者の7割もの方が加入しているといわれています。
しかし、利用率はこれよりも少なく、うまく活用できていない方が多いのが実情です。
パックプランなどで加入しているケースも多く、加入に気付いていない方も多いといわれています。
示談金を満額受け取るためにも、ぜひお手持ちの保険証書を一度ご確認ください。
4 もらい事故で慰謝料を増額したい場合は弁護士にご相談を
もらい事故の被害者は、当然ながら十分な補償を受け取る必要があります。
しかし、実際上は相手方の交渉術に負けてしまい、結果として損をしてしまうこともあります。
適正な金額の示談金を受け取りたい方は、示談交渉を弁護士にお任せください。
弁護士は、被害者が適正額の損害賠償金を受け取るためのサポートを行うことができます。
交通事故の示談金・慰謝料額でお悩みの場合は、どうぞ当法人にご相談ください。
死亡時の損害賠償 好意同乗・無償同乗中に交通事故被害に遭った場合の賠償金請求